子どもが不登校になり、やがて家から出られなくなる。
「人が怖い」「外に出るのが無理」と感じる子を前に、親はどう支えたらいいのか分からなくなりますよね。
実は、この段階で大切なのは“行動”よりも“回復”。
焦って動かすのではなく、まずは心のエネルギーを取り戻すことです。
この記事では、引きこもりの仕組みと、親ができる具体的な関わり方を、
不登校専門カウンセラーの視点からお伝えします。
動画でもお話ています
不登校とひきこもりの違い
子どもが不登校になると、
「外に出られない」「人に会えない」といった状態になることがあります。
そのとき親は、
「これは不登校?それともひきこもり?」と戸惑うかもしれません。
実はこの2つ、似ているようで全く違うものです。
-
不登校は、文部科学省の定義で
「年間30日以上、病気や経済的理由以外で登校していない状態」 -
ひきこもりは、厚生労働省の定義で
「6ヶ月以上、家庭にとどまり社会参加ができていない状態」
つまり、不登校の子が必ずしもひきこもりになるわけではありません。
外に出られない、誰にも会いたくないと感じるのは、
“心のエネルギーが尽きてしまった”サインです。
親が「外に出そう」「何かさせよう」と焦っても、
子どもにとっては息ができないほどつらいことなのです。
人が怖い、ひきこもる心理とは
子どもが「人が怖い」と感じるのには理由があります。
それは心のエネルギーが消耗しきっているからです。
学校で頑張りすぎたり、人間関係で傷ついたり…。
その中で、心がもう限界になってしまうのです。
エネルギーが空っぽの状態では、
人と話すこと、外に出ることが重荷になります。
だからこそ、子どもは無意識のうちに「誰とも会わない」選択をして、
自分を守ろうとしているのです。
ゲームや動画、寝続ける時間——
それらは怠けではなく、
心を守るための回復行動です。
また、性格(キャラ診断)によっても、
ひきこもり支援の対応には違いがあります。
-
おじいさんタイプ・末っ子タイプ:インドアが得意。家の中で充電できる。
-
おばあさんタイプ:長期の引きこもりで社会性が落ちやすい。
-
その他のタイプ:引きこもり=相当のストレス。まずは心の回復が最優先。
キャラについてはこちらで詳しくお話ています。
どのタイプの子でも共通して言えるのは、
「外に出られない」のではなく、
「今は出る元気がない」ということです。
家の中で最初に目指すこと
多くの親御さんが「このままでいいの?」と不安になります。
でも、最初に目指すべきは「居場所」でも「学校復帰」でもありません。
それは、家の中を安心できる場所にすること。
よく「家の居心地を悪くすれば外に出る」と言う人がいますが、
これは大きな間違いです。
ひきこもった大きな原因は
社会の中でいじめれらて傷ついたことです。
社会の中で傷ついた子にとって、
家だけが唯一の“安全基地”です。
だからこそ、まずは家を安心できる場所に整えることが大切です。
-
責めない
-
比べない
-
「いつまでそうしてるの?」と言わない
この3つを意識してみてください。
親が安心して受け止めてくれると、
子どもの心は少しずつ整い、
「ここなら大丈夫かもしれない」と思えるようになります。

動き始めた時の注意点
少し元気が出てくると、子どもにも動きが出てきます。
親としては「やっと外に出られるかも!」と思ってしまいます。
でも、ここで焦りすぎると、せっかくの回復が逆戻りしてしまいます。
特に引きこもりから動き始めた子は、
一気に頑張って、一気に疲れてしまうことが多いんです。
最初は本当に小さな一歩で大丈夫。
-
週に1〜2日、短時間の外出から始める
-
行き先は「安全に感じる場所」だけ
-
うまくいかなかったら、すぐに立ち止まって調整
これは「後退」ではなく、チューニングの時間です。
タイプ別に見ると、
-
長女タイプ・末っ子タイプ・おじいさんタイプ:ゆっくり地道に一歩ずつ進む
-
お母さんタイプ・長男タイプ・お父さんタイプ:勢いで進むが、燃え尽き注意
無理をさせず、「できたね」「頑張ったね」と声をかけてあげてください。
それが次の一歩につながります。
この動画のまとめ
子どもが引きこもり状態になったとき、
親ができることは次の3つです。
-
子どものしんどさを理解する
-
家を安心できる場所にする
-
一歩ずつ、子どものペースで支える
焦らなくて大丈夫です。
親が安心していれば、子どもは自然とエネルギーを取り戻していきます。
親子関係の「安心の貯金」が増えるほど、
子どもは自分の力で外の世界に向かう準備を始めます。
不登校の解決は「登校」ではなく、
親子が一緒に成長していくこと。
その先に、笑顔で過ごせる毎日が待っています。
親子でゆっくり整えていきましょう。


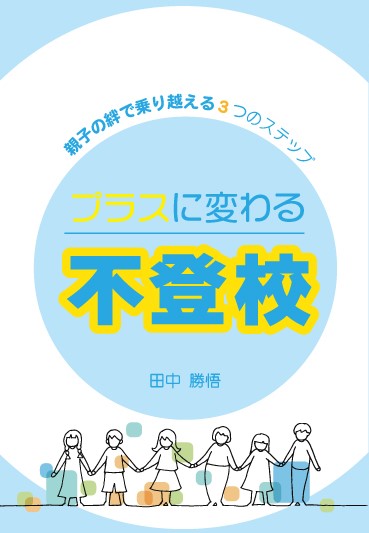
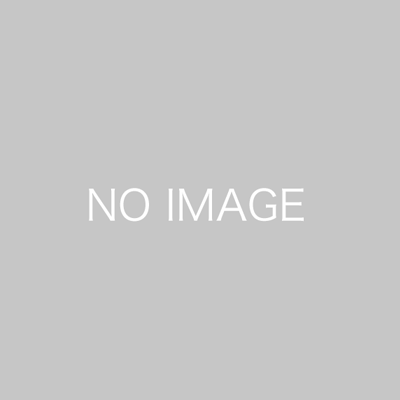
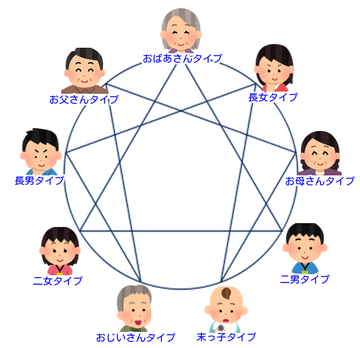
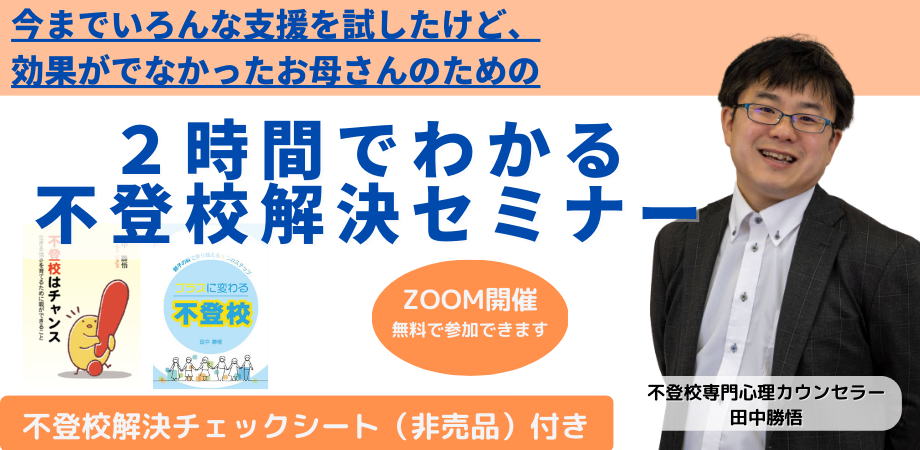
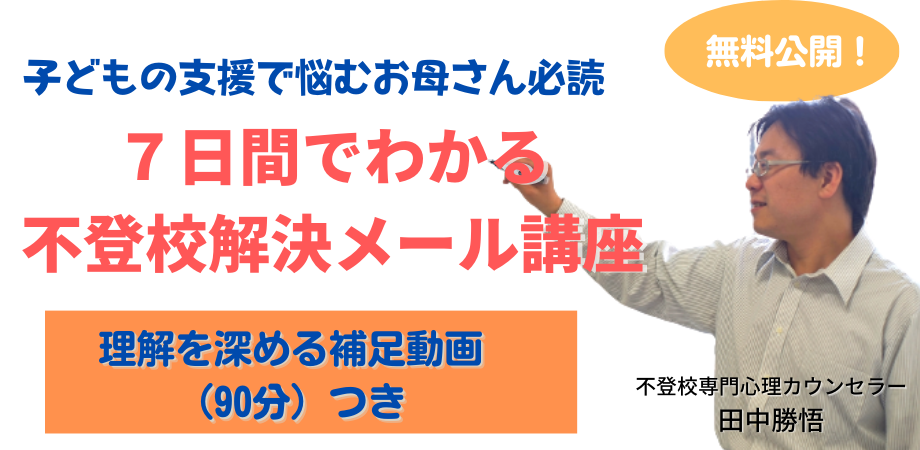

コメント
COMMENT